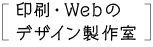言語化の効力
まずは筆者のお話を。
紙で原稿の叩き台をつくったり、パソコンに文字を起こしたりして、何かしらの考えを書き出す。
という機会が増えてきました。
「アウトプットが大事」ということを耳にされることがあるかと思います。
以前は「なんでアウトプットが大事なんだろう?」と思っていました。
ところが言語化(文章化)を重ねるうちに、あるメリットが感じられるようになってきました。
だからこそ、「アウトプットって良いな」と考えられるようになりました。
さて言語化することによってどんなメリットがあるのか、なぜメリットに繋がるのか。
ただの筆者の感想ではありますが、以下に言語化しました。
言語化がもたらす好影響への道筋
1.考えを書く
頭の中の考えは、漠然としています。
このモヤモヤを、紙や液晶に書き出します。
2.整理する
書いたものを箇条書きにしたり、文章を整理したりします。
そうこうするうちに、自分の意見がハッキリと固まります。
3.比べる
自分の意見がハッキリすると、別意見との違いが明らかになります。
違いが浮き彫りになるので、比較しやすくなります。
4.試みる
自分の考えや手法と、他人の考えや手法を入れ替えてみます。
5.取捨選択
合わなければ、元に戻す。
肌に合えば、続ける。
という選択を意図的に選べるようになります。
補足
“試す(4)”ことは、言語化しなくてもできそうです。
ただし“意図的に選ぶ(5)”というのがカギになるかな?なんて思います。
“自己意見(1-2)”を確立しておかないと、比較対象が曖昧で良し悪しが分からない。
となると、分からないことが分からないままで終わってしまう確率が高くなるのではないか?
という気がします。
まずは“比較(3)”するための目印を立てます。
目印とは、“自分の明確な意見(2)”です。
ウチとヨソとの違いが明らかだと、ヨソの良さにも気づきやすくなりそうです。
ヨソがいいなと感じたら、取り入れる。
合わなければ、やめてみる。
こんな改善サイクルが仕上がるんじゃないか?
といった補足でした。
さらに補足
選択の後「何が合わなかったのか」「何がどう良くなったのか」を言語化で理屈付けしていくと、再現性は高まりそうな気がします。
ただし結果と原因が一致するとは限りません。
予想の上積みに過ぎないため、自己結論に囚われすぎると、“偏見”や“誤解”に繋がりそうです。
結論に確信を持ちすぎると思考に歯止めがかかって、盲目的にになりそうだなと思いました。
(気がします・思います。ばかりで、なんですが)
まとめ
言語化の影響。
・自己意見がスッキリ整理される。
それに付随して、
・ヨソとの違いが明確になる。
・新手法のテスト結果を理屈付けすることで、再現性が高まる。
といった改善フローができあがる。
(ただし偏見や誤解に対する定期検診がいるかも)
そんなメリットがある気がしていますよ、という感想回でした。